|
【穂群原学園】には四階建ての校舎と渡り廊下で繋がっている物理室や化学室、コンピュータ室等がある特別棟、二階建ての体育館や弓道場が主にある。 志貴が居る位置は、職員室や事務室、会議室などが集まっている校舎の一階だ。二、三、四階には生徒たちのクラスがある。 かこん、と音がした。志貴がトランクケースを床に置いたのだ。ぱたんと開け、上履きとして下駄を取り出す。 下駄は音が響いたり、走るのには不適切なのだが、平穏な学園では何も起こらないだろう。編み上げブーツは下駄箱へ仕舞ったし、スリッパは今着ている蒼い着流しには合わないと志貴は思ったのである。校内の上履きとしては相応しくないが、志貴が通った学校の教員はスニーカーやサンダル等を上履きに使っていた人がいたから、一応許容範囲だろう。 漆黒の漆を塗られた黒い下駄。表面には艶があり、鼻緒は赤い。志貴は其れを履き、手首を返して肩にトランクケースを担いだ。背中に堅い革張りの鞄が当たる。此の格好はトランクケースではなくて布や革で造った袋を背負えば、明治時代に合うかもしれない。眼鏡を外せば、江戸時代にも合ってしまう事に、志貴は苦笑した。 リノウムの床を踏む。足許からは、からころと 志貴は二階へ上がった。イリヤの教室は此の階にあると大河から聞いていた。廊下には休み時間だから多くの生徒がいた。生徒の一人が志貴に気付いて眼を見開き、横にいる友達に話題を振った。 廊下を歩くと下駄が鳴り、廊下を歩くと生徒たちの視線が集まり、廊下を歩くと雑談の話題にされてしまった。 志貴はトランクケースを担いでいるのと反対の手で頬を掻いた。 視線は集まるのだが、目線は合わない。一瞬合うと逸らされる。だが其れが普通だろう。志貴も学校の廊下に和服で下駄の人が歩いていたら、話の話題にしてしまうし眼は合わし難い。 生徒たちの横を過ぎて行く。下駄の音がからころと、生徒の視線がずらりとなる。室内で下駄は間違いだったのかもしれないとも志貴は思った。否、学校で下駄は間違いだったのだ――とも思った。しかし代えのスリッパを持っている訳もないので、このままでイリヤの教室へ行く。 志貴は教えられた教室の扉に手を掛けて貌を入れた。教室の後ろ側だ。さらりと見回して、沢山の黒髪の中に一層綺羅びやかな髪の少女を見つけた。 イリヤは制服姿で髪形はポニーテールにして纏めている。伊達である四角い小さな赤縁眼鏡は彼女を知的に魅せていた。 イリヤは友達と窓際で話しているらしかったが、騒がしくなった教室に気付いて周囲を見回して志貴と眼があった。 イリヤは、はてなと小首を傾げて志貴を上から下まで視軸をずらして観察した。何故いるのか思考しているのだろう。 志貴はトランクケースを担いだまま、扉に掛けていた手を離してぴっと立てた。 「ちす、イリヤちゃん」 志貴は軽薄な挨拶をした。 教室の視線は志貴とイリヤへ集まった。 イリヤは一度小さく頷くと、駆け出した。人を避け机を避け椅子を避け、なるべく勢いを殺さぬ様に一直線に走る。 軌道の横にあった机の上から英和辞書を左手でばしりと引っ掴む。武骨な学習の友だ。 イリヤの姿勢は低く、低空滑空をする鳥の如く最小の動きで最短の軌道を描く。ポニーテールが空を踊り、辞書を持った左手はだらんと下げられ、辞書は躰の少し後ろの床をちりちりと疾る。 たんたんたんと軽快な跫が鳴る。志貴との距離が縮まって行く。 イリヤは一段低い体勢になり、赤縁眼鏡の奥の赤い瞳がきゅ、と細められた。下から志貴を見上げる。ぎゅうと床を踏み込む。上履きのゴムが摩擦で焼けて床に跡を付けた。 ぐんと背を伸ばす。勢いを殺さずに疾走を一瞬の瞬発力へ変え、辞書は円弧を描き、其の弾道は志貴の顎を狙っている。 一瞬の間。 武骨な凶器がぎゅんと打ち上げられた。 「わわっ」 志貴は声を上げた。後ろへとんと下がって躱す。 辞書は志貴の前髪を掠り、ぴんと弾けさせた。 イリヤは辞書を持った左手を頭の後ろまで上げて背をうんと逸らしており、ぱりっとした制服に隠れた適度な膨らみの胸が自己主張をしていた。辞書をえいと志貴に投げた。 志貴は挨拶をした手で、至近距離から結構凶悪な速度で打ち出された其れをぱしりと掴む。 イリヤは人差し指を志貴の貌へぐいと突き出した。志貴を見上げ、上目遣いで頬を膨らませて口先を尖らしている。赤い眼と黒い眼は、イリヤの眼鏡はずれており、志貴の眼鏡というフィルター一枚を挟んだ形で絡んだ。 教室はしんと静まり返っている。誰一人喋らない。突如現れた和服と学園のアイドルが、一触即発の状態にある。 生徒たちは和服とイリヤの関係に思考を走らせた。生徒たちが見てきたイリヤは、超然とした冷たい美貌と明るくて柔和な笑顔という相対した美を併せ持つ少女だ。言葉で大河を丸め込めた光景を見た事もある。何故和服に攻撃したのか。今何を云うのか。 イリヤは口を動かす。 「シキ、下履きで校舎内に入っちゃいけないのよ!」 耳を傾けていた者は肩をがたりと崩した。 そっちかよ。 問題ないよと志貴は応えた。 「これは校舎に入ってから卸したものだから汚れていない」 「そうなの」 イリヤはこてんと小首を傾げた。 志貴はこくりと頷いた。 「其れよりもほら、お弁当忘れていったよ」 志貴はトランクケースから白い弁当箱を取り出して差し出した。 ちょっと待ってとイリヤは云った。そして自の机の横に置いてあった、橙子から借りた武骨なトランクケースを志貴の下まで持って来て、ぺたんと床に座って箱の中身を確認する。 はわっ、とイリヤは驚いた。其れから志貴を見上げる。 「私のがない」 「だからほら、お弁当」 志貴は白い弁当箱をイリヤの眼前に差し出した。 イリヤはおずおずと其れを受け取った。そして胸に抱く。 「ありがとぅ、シキー。シロウのお弁当を忘れて行くなんて信じられなかったんだけど、届けてくれて本当にありがとぅ」 イリヤはぺたんと座って志貴を見上げ乍ら、微笑みをほんわかと浮かべた。 「まだ民谷氏の冬木市へ入る手続きは終わってないです」 司書である女性は云った。 学園の図書室である。 「妹の方は問題ないですけど、兄の方で行き詰まっているです。兄である 司書はけけけと短く笑った。善く喋る女性である。 全体が小作りで、小さめで切れ長の奥二重が印象的である。大きめのワイシャツと薄い灰色のジーンズ。派手な訳ではないのだけれど、そして取り立てて美人とか不美人とか云う事もないのだろうが、話し出すと目立つ。志貴よりも年上なのだが、雑気があって小娘のようだ。 志貴は椅子に深く腰掛けて溜息を吐いた。予定が思うように進まない。此れでは駄目だ。何か手を打たなければならぬ。 彼女は、日本における神霊事象を統括する『内閣直属霊的防衛機関陰陽寮皇土管理局』の『戦術士』の一人である。『派遣戦術士』として【冬木市】における事象現象を観測し記録し、一等霊地である【冬木市】と『陰陽寮』を繋ぐ者である。しかし繋ぐと云っても特にやる事はない。『陰陽寮』は【冬木市】の権利を『協会』と『教会』に奪われており、直接干渉する事は出来ぬ。ただ観測するだけで事故処理もしない。 そして。 『陰陽寮』に帰属する者は【冬木市】には彼女しかいない。其れに彼女は、7年前から【冬木市】にいるらしいが、 志貴が図書室に来た理由は、時間に空きが出来た為であった。イリヤに弁当箱を渡した時に、休み時間は終わりそうになっていたので二言三言しか会話を出来なかった。短い会話の中で、昼休みに屋上で一緒に昼食を摂ろうと云う事になり、其の空いた時間に司書を訪ねる事にしたのだ。 『戦術士』でもある司書と会う事は、志貴が今まで学校に無断侵入していた理由の一つである。血液に関する魔を探求している魔術師、否 別の場所では駄目なのか――志貴は髪の毛を掻き毟った。 「【冬木市】でなくとも都合がつく場所はあるだろう。俺は、ここでなくてはいけないと云う訳ではないんだ」 「君のその言葉はこれで何度目だか覚えているですか。8回です8回。あたしに何度も同じ事を云わせないで下さいです。――云ったでしょう。《『殺人貴』が【冬木市】で『護幻帝士』と会見する》と云うのが重要であると、つまり《『協会』と『教会』の【冬木市】へ『陰陽寮』の『護幻帝士』が滞在する》と云うのが重要なのです。私のいけ好かない上司が云ってたです。あの狸は『陰陽寮』の【冬木市】の干渉権を少しでも得たいようですよ。だから我慢です。民谷氏も【冬木市】の重要性は解るそうですけど、さっさと済ませたいようですし」 司書は両腕で膝を抱えて椅子に踵を乗せ、膝の上に顎を置いた。 だがなと志貴は云った。 仕方ないですと司書は片手を広げて突き出し、志貴の言葉を遮った。 「それに君は、前回の『聖杯戦争』の生き残りたちとよろしくやってるみたいですから、もう『姫君』の事なんか――」 司書は突然、ぐうと唸った。頬が 何もされていない筈だ。しかし心臓は激しく喉許で打ち始め、酷い寒さに出遭った様に体がぶるぶると震え始める。内蔵がぐうっと収縮し、目の前の景色が廻り始める様な予兆に囚われた。 ただ。 司書の眼の前の志貴が表情を消していた。感情が消失して能面の様である。まるで死相だ。生者の持つ表情ではない。死人の面。頬に赤みはなく、青白い。眼鏡越しの両眼が薄く細められている。凶相という訳ではないのだけれど、司書は志貴の無表情に威圧される。 「――失言でした。情報が、届いたら知らせるですから、出てって下さいです」 司書は掠れた声でそう云った。 志貴は椅子から 司書は、志貴が来る前まで読んでいた本を再び開いた。活字に視線を落とすが、全く読めない。本はかたかたと震えている。否、司書の手が震えていた。溜息を吐き、本に栞を挟んで大きな机の上にぽいと投げた。本はからからと滑り、机の中央で止まった。 ――殺人貴ですか。さっさと冬木から出て行ってくれないですかね。壊れた存在ですよ。 司書は再び溜息を吐き、机の上に身を投げ出して突っ伏した。不貞寝である。睨まれてから平静を保っていたつもりだったが、そんなことは出来なかった。 司書は常人の世界とはずれたモノを視ている超能力者だが、遠野志貴は更にずれたモノを視る者であった。あそこまで壊れていて、未だに生きていることが信じられぬ。 【千年城】で眠りに就いたと聞く、 ――けど、可哀想な存在かもしれないですね。 司書はまた溜息を吐いた。 志貴とイリヤは、季節が初冬となって気温が低くなっているのに関わらず、学校の屋上に居た。志貴は和服の上に蒼い布を羽織って壁に 寒くないかと志貴は尋いた。 「寒くないわよ」 「本当?」 「ちょっと寒いかも」 イリヤははにかむ 「あったかぁい」 志貴は苦笑した。わざわざ屋上でなくても良かったと思う。けれども好奇の視線に晒されなくて済む処で食事を摂れるなら、寒さを我慢してまで此の場所に居ることを良いとも思う。 「ねえ志貴。どうしたの?」 イリヤはカップを抱えたまま上目遣いで唐突に尋いた。 何が、と志貴は首を傾げて聞き返した。 「ぴりぴりしているというかどろどろとしているというか、巧く表現出来ないんだけど、何か変よ」 志貴はイリヤの瞳をじっと 「鋭いね、イリヤちゃんは」 志貴はイリヤに見透かされていると思ったことが多くある。彼奴よりも赤みが薄い瞳が、志貴が知らずに肚の底に溜まめてしまった様様な思惑をも掘り起こしているのではないか――とも思う。 しかしそれは志貴の幻想で、イリヤの魔眼にはそんな力はない。ただ自分というモノが希薄だった為に、周りの変調に敏感なだけだ。一般人にも其れぐらい感じられる者はいるが、相手を想うが故に感じられるのではなく、人形であったが故に周囲の泥を感じられるのである。 「民谷との件が全く進まないことが、ちょっとね」 志貴は湯飲みに視線を落とし、司書に云われた民谷氏の件の内容を話した。 イリヤはカップを口許で留め、時折傾け乍ら話を聞いていた。湯気によって赤縁眼鏡が曇ってしまったときはあるが、気にしていなかった。 「ふぅん。組織に属している者だから、政治的な問題は避けられないのね。『陰陽寮』は『協会』よりも組織的だし、上下階層の厳しい処らしいわ。日本の特色かしら」 「そう、だからまだ駄目みたいなんだ」 「けれど志貴――」 イリヤはすらりと立ち上がり、四角い赤縁眼鏡を外してポニーテールに束ねていた髪を解いた。絹糸のような髪がぱらぱらと広がる。 志貴は、突然のイリヤの行動に眼を丸くして戸惑った。其れは、イリヤスフィール・フォン・アインツベルンの魔術師としての姿だった。 「――民谷の魔導で『姫君』を助けられると思っているの」 びきり、と 其れを酷く冷たいと思った。 「魔術師として言わせて貰えば、今の時代で吸血衝動の解明解決は不可能よ。あの『魔導元帥』でさえ呪いの解呪が出来ない。それに現代の魔術師は、衰退する一方だから期待出来ない。民谷がどう行った道筋で『根源の渦』を目指しているのか知らないけど、吸血衝動を研究することは本筋ではないでしょう。それに衝動の解決は、どちらかと云えば医療にも含まれるんでしょうね」 其れはシオンから聞いたことがある。月落としを素手で受け止め、『究極の一』朱い月を倒した魔法使い。『 「私たち魔術師の魔導体系は、 「それは――」 イリヤの云いたいことは解る。 志貴はカバラとか陰陽道とかよく解らないが、吸血衝動を解明解決出来た者は居ないことを知っている。『分割思考』『高速思考』の錬金術師シオン・エルトナム・アトラシアの計算でさえ、答えが出ていない。 彼女から聞いた魔導の在り方。公としての技術 其の問題は、志貴の思考をぐらつかせる。 「今まで吸血衝動を研究して来た魔術師は多く居るわ。その事如くが行き詰まったけどね。でも彼らが研究していたのは 「――そうかもしれない。けどね。少しでも関係する情報があるのなら、俺は知りたい。衝動を抑える為にずっと城で寝てる彼奴を、叩き起こしてやりたいんだ」 志貴は座ったまま鋭く眼を細めてイリヤを見上げた。 イリヤはトランクを迂回して志貴の眼の前に立った。膝と腰を曲げて志貴が凭り掛かっている壁に右手を当てた。志貴の貌が近くにある。 志貴はイリヤの眼をじっと凝乎る。大きな紅い瞳に志貴の貌が写っている。其れを縁どる、濡れた様な白の、長い長い睫。淡雪の如き白い肌。すっと伸びた高い鼻と形の善い桃色の口唇。陰光で 小さな口唇が動く。 「真祖の姫をどう思っているの」 「愛している」 「何がしたいの」 「時間を共に」 「何故」 「殺した責任は、俺がとる」 志貴が答えると、イリヤは壁から手を離して背を正し、眼を細めて柔和な微笑みを浮かべた。 「うん、好い眼と言葉ね。 志貴、魔導世界に不可能な事象はないわ。 だから頑張ってねとイリヤは云った。 其の言葉は、思うように行かなくて不安定になっていた志貴の心を安定させた。政治的な問題や魔導の可能性への不安など、様様な揺らぎを拭い去った。現状が変わった訳ではない。志貴の意志を強固にさせた。 女は強いな、と志貴は思った。どの年齢の女性でも、芯がしっかりとしている者の言葉は他者に影響を与える。 「――ああ、頑張るよ」 志貴は口許を綻ばして微笑みを返した。 靴と床の擦れる音と球の弾む音が、広い空間を保有する体育館の中に響き渡っていた。きゅっと靴底のゴムが灼け、ダンダンと球が床に叩きつけられる。イリヤのクラスは6時限目、男女別でバスケットボールであった。イリヤの隣のクラスとの合同授業である。 志貴は体育館の二階観戦席の手摺に、和服の袖の中で腕を組んで肘を乗せ、イリヤが居るチームのゲームを観ていた。足下にはトランクが置いてある。 高校の時、体育は貧血持ちということで見学をするのが多かったので、見学することで生徒たちのやる気がある娘とない娘が ゴールが入ったときに、歓声が上がる。一人二人良い動きをする娘が居た。バスケ部なのだろう。人が球を追い駆けて人が人を追い駆ける。 イリヤは其の中に居た。結い上げたポニーテールが走る度に上下に波打ち、流れた汗が白い コート上を走り回る小娘らが写っていた志貴の視界の端に、ざらざらとした黒い澱が滲み出て来た。雲一つ無かった晴天が、突如空の奥から滲み出た暗雲に覆われ始めた様に、ひりひりと木造の体育館が変わって行く。しかし。 一向に女子生徒たちに変化はない。黒い澱が滲み出て来たのに、イリヤでさえ気付かぬ。ならば此れは、魔導を識る識らぬは関係のない事象であると云うことだ。魔導の造詣の浅い志貴が視えるのは、如何なる理由か。考えずとも思い付く理由は一つある。 死を視る眼。直死の魔眼である。 ――またか。 壊れた眼と脳髄が視せる常人とは別の世界は、先生から貰い受けて橙色に調節された眼鏡をもってしても、志貴を浸食することを停めなかった。 志貴は口許を押さえた。喉元まで来ていた錆び付いた味のする物を溜飲する。口内にざらりと匂いがこびり付いた。血の味だ。 ――長くは、ない。 躰の調子は悪くない。日増しに機敏に動く様になっている気もする。否、気もするではない。そうなっている。しかし其れは、生を贄として得た異能である。命を蝕む力だ。 健常者と比べ、死を識るという壊れた脳髄は、躰さえも造り変える。死に触れ易い様に死に近付く様にと組み替えられる。 死とは停止だ。此の先5、60年ある寿命を大幅に縮めて志貴は存在する。故に圧縮された生命は、肉体の既定限度を超えた力を可能とする。俗に火事場の馬鹿力と云うものだ。死へ加速する諸刃の力である。 造り変えるといっても、人類種の範疇でしかない。人間に吸血鬼という概念を被せられた死徒。人間に死という概念を被せられた殺人貴。不死に近いモノと死に近いモノ。ベクトルの異なる力の顕れ。 故に此れでは、残り10年も生きられぬ。5年ぐらいが妥当だろう。其の前に彼奴の呪いを解かねばならぬ。 志貴は息吹を繰り返す。躰を落ち着かせる為の呼吸法である。死への急な加速を止められぬのなら、眼と脳髄を制限し、せめて出来るだけ緩やかにする。今は其れしか方法がないのだ。彼奴の呪いを解呪するまでは死ねぬ。 暫くすると、視界の 志貴は溜息を吐き、胸を撫で下ろした。階下に視軸を移すと、イリヤたちのゲームが丁度終わる処である。ブザーが鳴り響いた。 イリヤがコートの中央で此方に手を振っていたので、志貴は片手を上げて応えた。如何やらイリヤのチームが勝ったらしい。其れからイリヤは、此方に向かって球を抱えたまま走って来た。 イリヤは志貴の眼下に立って見上げた。 「いつまでも上に居ないで、下に降りて来たら」 「そうだね。それも良いかもしれない。じゃあ今から降りるよ」 志貴はそう云うと、革張りのトランクを持って2階観戦席から階段へと歩を進めた。 志貴は手摺から飛び下りることも出来たが、遠坂凜の再来と教師たちに囁かれている学園のアイドルであるイリヤスフィールと仲が良く、珍しい服装をしているということで目立っているのに、更にまた目立つ行為をすることは憚られたので、階段を使うことにしたのである。 志貴は、コートの外に立つイリヤの隣に立った。 「思ったよりも運動神経良いんだね。あれはインドアな職種なのに、随分と体力がある」 「そうね。私は前に、神父に抱えられるなんて屈辱を受けたときがあるから、今度ああいうことにならないようにって、最低限体を鍛えているの」 「へぇ」 志貴はコートの端にトランクを置き、其の上に腰掛けて右膝に左足首を掛け、前傾し猫背になって左肘を左足の上に乗せ、左掌の上に顎を乗せた。 改めてイリヤを観れば、遠くからでも思ったが、ブルマ姿がとても似合っていた。情欲の類いではなく、幼子が砂場で遊んでいるのを観たときの様な保護欲をかき立てられる。けれども口には出さぬ。言葉にすれば、イリヤを辱めるものにしかならぬと思ったからである。イリヤの容姿は幼いが、幼子と呼ばれる年ではあらぬ。 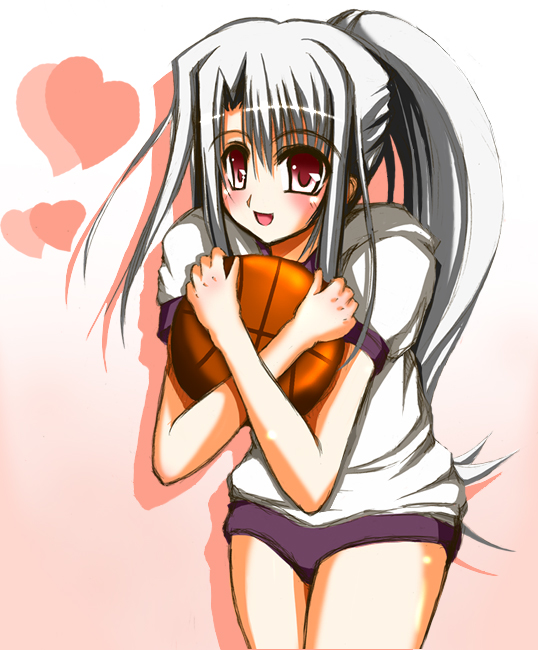 絵 双葉さん
「ねぇ志貴。暇みたいだから一緒にバスケやってみない」 絵 双葉さん
「ねぇ志貴。暇みたいだから一緒にバスケやってみない」はァ、と志貴は呆れた声を上げた。 「そんな授業参観で父兄が乱入するみたいなまね出来ないよ。それにほら、他の生徒の邪魔になるからさ」 「じゃあみんなが良いって云ったら出るのね。 ねェ、聞こえていたんでしょ。シキがゲームに入るのは厭だって人は手を上げて」 えっ――志貴は、周囲をぐるりと見回したイリヤを見、それからイリヤの視軸の先を見た。手を上げる者は一人も居なかった。 「ほらっ、反対者なし」 志貴は溜息を吐いた。 「こういうのは、大体がどっちでも良い人なんだから、尋き方次第で変わると思うんだけど。それに俺、バスケは苦手なんだよ」 「気にしない気にしない」 イリヤはトランクの上に座っていた志貴の襟首を掴んで、コート中央までぐいぐいと引っ張っていった。 結果。志貴の入ったチームは大差で負けましたとさ。 第三章 少女の学校 終幕 あとがき 其の一 [冬空の下]は、改訂前の三章であった『陰陽寮』を掲載してしまうと、残り三話で終わってしまいますから、その前に書いてみたいエピソードを入れることにしました。 学校などです。 桜とライダーの絡みが好きです(笑) 其の二 二人乗りで坂道なんて並の人には無理です。実は志貴よりアーチャーの方が自転車が似合っていると思ったり(笑) イリヤの勘違いからの一撃の描写は二、三行で済みそうなのに、何故か戦闘描写を使ってました。まあその後の笑顔とメリハリが効いてて良かったかな。 作者的にはぺたんと座ってトランクの前で、はわっと驚いたイリヤがお気に入りです 其の三 ただ志貴×イリヤではなく、志貴とイリヤの絡みを多く書こうということにしました。イリヤはお姉ちゃんです。うだつのあがらないヘタレな奴には、喝を与えてくれます。 次章はイリヤ視点で展開したいと思います。 其の四 ポニテブルマイリヤ。 志貴の欠陥は大変そうなのに、CGにおいしいところ喰われています(笑) 双葉氏に感謝。 それでは |